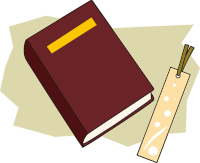 中学校と高校のことを書きますが、世の中の出来事、本を読んだこと、人との出会い、このようなことが重なり今の自分があるんだなと思います。
中学校と高校のことを書きますが、世の中の出来事、本を読んだこと、人との出会い、このようなことが重なり今の自分があるんだなと思います。
中学校では授業以外の勉強をした記憶がありません。なにしろその頃は勉強で競争するということを知らなかった。小さい頃から知ってる仲間ですから、勉強でも運動でも序列が決まっているんです。先生方も宿題を出すわけでもないし、村には本屋がない、勉強の参考書やましてや問題集などというものは存在しなかった。学校の中に図書室はあったんだろうか?図書室の中で何かを調べた記憶はないし、本を借りたこともなかった。
中学校3年生の時に弘前市内の中学校も参加した高校入試の模試があった。3回はあったと記憶している。模試の結果を見ると、附属中学校や一中などほぼすべての中学校が参加していたが、成績優秀者のリストに名前が載っていた。このこともあって家で勉強する必要がなかったのです。
弘前高校には余裕で合格しました。そして、入学するまでに本を読んでくるようにという課題が出ました。何冊かの中から私は太宰治の「津軽」を選びました。この本が教科書以外で読んだ1冊目の本でした。何と私が知らない世界がいっぱいあること!教科書で名前は知っていましたが、太宰治についていろいろ知りましたし、津軽には7つの雪があることも初めて知りました。これを契機に今はなくなりましたが「今泉本店」に通っていろいろな本を読むようになりました。
弘前高校に入ってショックなことがあった。1年生の最初の実力テストでのことです。その頃は試験をやると成績上位のリストが公表されていました。そして自分が学年で何番かということも知らされました。何と400人中120番だった。これではいけないと思い勉強を始めました。今泉本店にも出入りしていたので参考書も問題集も簡単に手に入ります。2年生になるとこの努力が実り、将来の可能性が広がりました。
高校1年生の時に札幌医大で心臓移植が行われました。当時はすばらしい最先端の医療で、世界で30番目に行われた手術と報道されました。しかし、その後、脳死判定の問題、手術そのものが適応だったのかなどと問題が提起されました。その中で札幌医大整形外科の医師である渡辺淳一は「ダブルハート」を出版し心臓移植に対して疑義を挟みました。渡辺淳一はこの件で札幌医大にはいられなくなり作家に専念することになりました。
高校2年生の時は今泉本店で小林綾という人が書いた「部落の女医」という本に出会いました。部落というのは村の小さい集落のことですが、今は差別用語として使われなくなりました。テレビでは女優という言葉は使われなくなり女性も俳優と言われています。女医という言葉も今では差別用語なのでしょう。西目屋村には診療所がありましたので寒村での医療のことを想像して買ったのですが、何とこの本は私が知らなかった被差別部落のことを書いた本でした。
札幌医大で心臓移植が行われたこと、「部落の女医」を読んだこと、このようなことが重なり、私は将来は医師になろうかと思い始めました。高校2年生の頃です。当時、弘前にはJRの前身である国鉄の診療所がありました。伯父が国鉄に勤めていたことから診療所の医師と知り合いになりました。その医師は医学のことよりも医療のことをいろいろ教えてくれました。そして、「弘前で医者をするんだったら弘大に入りなさい」とアドバイスをしてくれました。
そこで医学部に入るために第一志望を弘大、滑り止めを札幌医大に決めました。札幌の試験会場で隣に座ったのが浪人している受験生でした。話をすると、「お前はバカだ!」と。「札幌医大は道立で、北海道以外からは定員の20%しか採らない。だから北海道以外から受験して札幌医大に合格するような人は北大医学部に合格するんだよ!札幌医大は滑り止めにはならないんだよ!」と。後で調べてみると、確かに北海道以外からの合格者数は毎年きっかり20%でした。
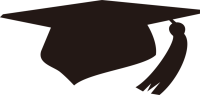 札幌医大には合格しました。その後、弘大にも合格しました。当時は弘大の合格発表は3月末でした。そこで4月1日に札幌医大に入学辞退の連絡をしました。すると、「4月1日は新年度になるので学籍に載ります。辞退届ではなく退学届を出して下さい。」とのことでした。ですから、私は札幌医大を退学して弘大に入学したことになります。
札幌医大には合格しました。その後、弘大にも合格しました。当時は弘大の合格発表は3月末でした。そこで4月1日に札幌医大に入学辞退の連絡をしました。すると、「4月1日は新年度になるので学籍に載ります。辞退届ではなく退学届を出して下さい。」とのことでした。ですから、私は札幌医大を退学して弘大に入学したことになります。
例の浪人生には弘大の入試の前に土手町でバッタリ出会いました。そして、「弘大を受けるべきでない。札幌医大は辞退しても補欠を繰り上げ合格させない。だから弘大を受けるということは日本から医師を一人少なくすることだ!」と。確かにそうだったようです。
第140号より